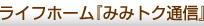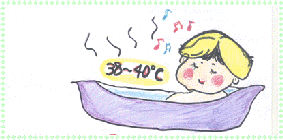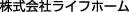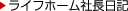梅雨時の体調管理
梅雨時の体調管理
暑くて湿った気団によって作られる高気圧である
太平洋気団と冷たくて湿ったオホーツク海気団が日本の真上当りで
おしくらまんじゅうをしてできたのが梅雨前線という事になります。
暑い夏が来る頃にバテバテにならないように
今回は梅雨に体調管理の特集です。
なぜ?体調崩しやすい季節?
梅雨時期に体調の変化が起こりやすくなるのには理由があります。
人のからだは、恒常性(ホメオスタシス)という性質があります。
気温の変化にあわせて体温を調整するのもそのひとつ。
4月から気温が上りはじめますが、
6月頃身体がやっと慣れ始めたときに梅雨が始まります。
梅雨時は、気温や湿度が大きく変化するため
からだの恒常性がついていかなくなり、体調を崩してしまいます。
冷房も使い始める季節。冷えを感じて自律神経も乱れることも。
気分の憂鬱さ、
からだのだるさや疲れ風邪をひきやすいなどなど。
梅雨時に毎年調子が悪くなる人もいるようです。
やってみては?
梅雨対策
太陽の日にあたろう!
太陽の光をまったくあたらない生活をしてると
ウツウツしてしまいます。
気分をリセットする意味も、
体内時計を整えて睡眠の質をよくする効果もあるんです。
雨の晴れ間にはちょっとでもリフレッシュ!
お気に入りの傘を購入する
雨が降っていやだなぁとか
思って会社に行くよりも大好きな傘なら
雨の日も楽しいではないのでしょうか。
天気予報で毎日天気を確認
雨が降る、降らないではなく
気温の変化をきちんと把握することで
風邪をひかないように体調管理ができます。
寒い日は上着を持ってでましょう。
お風呂で半身浴
冷房の部屋にいると皮膚の抹消の血行が悪くなり、
汗をかきにくくなるため、汗腺の機能が落ちているため、
熱がからだに貯まってしまうんです。
38~40℃ぐらいのぬるま湯で半身浴がおすすめですよ。
お風呂に入って、汗をたくさんかくと汗腺の働きがよくなります。
ゆっくり 湯船に使ってリフレッシュしましょう。
2013.06.24
シンプルマナー生活
シンプルマナー生活
今の私達のくらしは形式にとらわれず、自由です。
でも、その自由さがかえって不自由さを感じてしまいます。
「冠婚葬祭事典」で調べようとしても
時代の変化でずれもあります。
つい不安になって無難な「しきたり」に合わせてしまい
また現実の暮らしの感覚とずれたり。
で、最近図書館で手にした本。
「シンプルマナー生活」著者:辰巳渚氏。
当たり前のようで
あたり前でない自由の時代。
シンプルなマナー生活。
贈り物の常識
Q 数や量が少ないと相手に失礼?
A 家族の人数は少ないのに物や食べ物があふれている現代、
「少なすぎて失礼」よりも
「多すぎて困る」のほうが切実。
美味しいものを、心を込めて、ちょっとだけお届けする。
目安は相手が一回で食べきれる量。それが心配りです。
Q お中元・お歳暮はいつやめればいい?
A お中元、お歳暮はその年にお世話になった人に感謝を贈る事。
続けることに価値があるわけではない。
感謝の気持ちが薄れて「やめたいな」と思った時がやめどき。
贈られる相手にすれば届けばうれしいけど、
届かなくても「今年はこないな」で終わる話。
逆に両親や親しい友人など
心から今年もありがとうと感謝したい相手には楽しんで
お中元、お歳暮を贈り続けたい。
Q 結婚祝いに2万円はダメ?
A しきたりの知識が日常生活とずれていたら
知識を修正するべきです。
ぴんとこない「不吉な数字」などタブーでもなんでもない。
実質的には意味がないに等しい。
現代では、どんな場合でも4だけ気にすればいい。
「4個」はそれほどでもなく
「4万円」だけ気にすれば問題ないのである。
電話・メールの常識
Q ○○さんのアドレスを教えてといわれたら
A いくら親しくしてても本人の了解を得ずして
他人に教えないのがルールです。
いったんインターネット上に流れてしまうと
どんな使われ方をするか予想がつかない危険性があります。
友人関係に亀裂が入らないためにも守りたいですね。
あと、人のメールを転送しないのもルールです。
メールは文字の記録として残ってるぶん、
気軽に転送すると思わぬトラブルにもなりかねません。
この場合も承諾が必要。
社会生活の常識
人にぶつかったら必ず謝る。
歩行者の多い通路では自転車から降りる。
迷惑電話は話の途中でも切ってもよい。
など63項目.。
とても参考になります。
当たり前の事が文章にされると
改めて逆にどうでもよい事に気をとられてる気もします。
今、物があふれた時代、
断捨離という言葉や本が爆発的に売れました。
物や情報があふれた今の時代を少し
変えてすっきりしたい、って思う人も多いはず。
いらない常識も山ほどあります。
一度自分のなかで
本当に大切なことをまとめてみるといいかもしれません。
たとえば。
深夜のメールの返答は朝にするなど。
暮らしのマナーやルール。
ほとんどのことは私達はわかっていること。
本当の意味で自分の暮らしを豊かに
楽しく温かいものにしたいですね。
2013.06.05